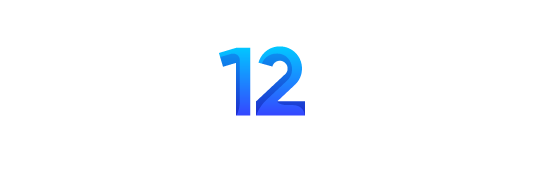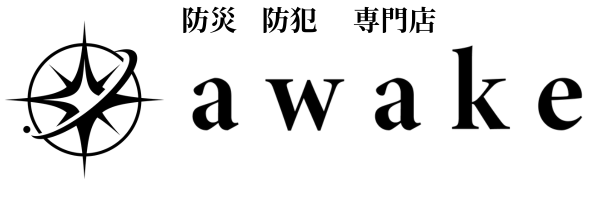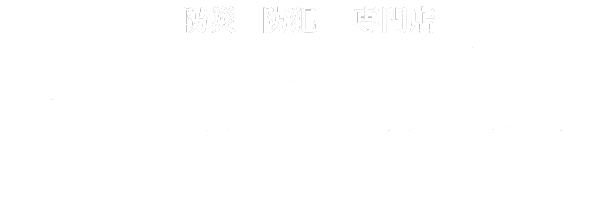はじめに:防災に「食料の備え」が欠かせない理由
地震、台風、豪雨、停電、断水――
災害発生時、最も困るのが「食べ物と水が手に入らない」ことです。
コンビニやスーパーの棚はすぐ空になり、物流も止まります。
そのため、家庭・職場・学校・自治体では最低3日分、できれば1週間分の食料備蓄が推奨されています。
この記事では、
- 防災用の食料をどれくらい備蓄すべきか
- 非常食と保存食の違い
- 家族構成に合った備蓄計画
- 実際におすすめの防災食・人気メーカー
これらを最新の防災ガイドライン(内閣府・消費者庁推奨)をもとに詳しく解説します。
もくじ
防災食料とは?非常食・保存食の違い

「防災食料」という言葉には、主に以下の2種類があります。
| 区分 | 名称 | 特徴 | 保存期間 |
|---|---|---|---|
| 非常食 | Emergency food | 災害時にすぐ食べられる食品(加熱不要) | 約3〜5年 |
| 保存食 | Long-term preserved food | 長期保存できる一般食品(加熱が必要な場合も) | 約1〜10年 |
非常食の例
- アルファ米(お湯・水で戻せるご飯)
- 缶詰(パン、魚、肉、果物など)
- レトルト食品(カレー、丼、スープなど)
- クラッカー・ビスケット
- エネルギーバー
保存食の例
- レトルトご飯・冷凍食品
- カップ麺
- 栄養補助食品
- ミネラルウォーター
- インスタント味噌汁
防災用食料の備蓄量の目安(家族構成別)
家庭の場合(大人2人+子ども1人)
| 食品 | 1人1日あたりの目安 | 3日分の目安(家族3人) |
|---|---|---|
| 飲料水 | 3リットル | 27リットル |
| 主食(ご飯・パン) | 2食分 | 18食分 |
| おかず・スープ類 | 2〜3品 | 約20食分 |
| おやつ・甘味類 | 少量 | 約9食分 |
ポイント:
- 飲料水は「飲む分+調理用」を含めて1人1日3Lが目安。
- 食料は家族構成・アレルギー・年齢・宗教などに応じて準備。
- 子どもや高齢者にはやわらかい・塩分控えめのものを選ぶと◎。
防災食料の選び方のポイント
【保存期間】長く持つか
近年では、5年〜10年保存可能な防災食が主流です。
特に企業・学校・自治体は「7年保存食」を選ぶケースが増えています。
【調理不要】すぐ食べられるか
災害時はガスや電気が使えないことも。
「開けてすぐ食べられる」「水だけでOK」な食品を優先。
【栄養バランス】主食・副菜・デザートを意識
ご飯やパンだけでなく、たんぱく質・ビタミン・糖分も必要です。
缶詰(ツナ・サバ・果物)やスープ、ようかん、ビスケットなども組み合わせましょう。
【アレルギー・宗教対応】
防災食の中には「アレルゲン不使用」「ハラール認証」「グルテンフリー」など、
多様なニーズに対応した製品も増えています。
ローリングストック法で無駄なく備蓄!

「備えたけど賞味期限が切れてた…」という失敗を防ぐ方法が、ローリングストック法(回転備蓄)です。
方法
- 普段食べる食品を少し多めに買っておく
- 古い順に使い、使った分を買い足す
- 常に一定量の食料が家にある状態を保つ
例:レトルトカレー・缶詰・乾パン・水を常にストック
使ったら新しいものを補充して“食べながら備蓄”
これなら非常食をムダにせず、新鮮に保てるため、家庭でも続けやすいです。
人気の防災食・おすすめ商品10選(最新版)
尾西食品「アルファ米シリーズ」
- 特徴:お湯・水で戻すだけ。五目ごはん・ドライカレーなど味豊富
- 保存期間:約5年
- アレルギー対応あり
イザメシ(IZAMESHI)
- 特徴:おしゃれな防災食ブランド。常温で美味しい
- メニュー:煮込みハンバーグ・ごはん・スープなど
- 保存期間:約3年
アルファー食品「安心米」
- 特徴:災害時でも美味しいと評判。外国語表記対応
- 保存期間:5年
尾西のひだまりパン
- やわらかくしっとりした缶入りパン。甘みがあって子どもも食べやすい。
カゴメ「野菜一日これ一本 長期保存用」
- 野菜不足を補うビタミンドリンクタイプ。保存5年。
日清「カップヌードル保存缶」
- 特別仕様のカップ麺。災害時でもホッとする味。保存3年。
キューピー「やさしい献立」シリーズ
- 高齢者・子ども向けにやわらかく、飲み込みやすい防災食。
森永「えいようかん」
- 手軽にカロリー補給。甘みでストレス軽減。保存5年。
UAA食品「カレー職人 ロングライフ」
- レトルトで7年保存可能。ご飯とセットに◎。
コクヨ「備蓄セット・防災バッグ」
- 食料・水・ライトなど一式が入った法人向け防災パッケージ。
法人・自治体向け防災食料備蓄のポイント
企業や学校では「72時間(3日)分×従業員数」を基本に備蓄が求められます。
また、近年は「在宅避難対応型」「備蓄+配布併用型」などの新しい形も登場。
備蓄運用のポイント
- 消費期限を一括管理できるシステムを導入
- 在宅勤務者向けに非常食を配布
- 避難所・オフィスでの炊き出しも想定
例:「オフィス防災 EXPO」などの展示会では、法人用の長期保存食が多数出展されています。
非常時に食料を確保できない場合の工夫
- 水なしで食べられる食品(ゼリー飲料・ようかん・乾パン)を常備
- 電気が止まっても使える「ガスボンベ式コンロ」を備える
- 冷凍庫の食材は「停電後48時間以内」に調理・共有
- 災害直後は「地域の炊き出し・配給情報」を確認(自治体HP・防災アプリ)
よくある質問
Q1. 防災用食料はどれくらい備蓄すればいい?
→ 1人あたり3日〜1週間分が目安。飲料水は1日3リットルが推奨。
Q2. 賞味期限が切れた非常食は食べても大丈夫?
→ 未開封・変色や異臭がなければ問題ない場合もあるが、安全のため交換推奨。
Q3. 赤ちゃん用・高齢者用の防災食はある?
→ あります。離乳食、防災ミルク、高齢者向けやわらか食などを選びましょう。
Q4. アレルギー対応の防災食は?
→ 「特定原材料7品目不使用」「ハラール対応」など明記された商品を確認。
防災食料の管理と定期チェック方法
| 項目 | チェックポイント |
|---|---|
| 賞味期限 | 半年〜1年ごとに確認 |
| 保存場所 | 高温多湿・直射日光を避ける |
| 家族構成 | 年齢・好み・健康状態に合わせて見直す |
| 補充タイミング | 消費または賞味期限1年前に交換 |
スマホのリマインダーや防災アプリで期限アラート管理を設定しておくのもおすすめです。
まとめ|“食の備え”が命をつなぐ
防災対策の基本は「水・食料・情報」です。
中でも食料は、命をつなぐ最も身近な備えです。
- 家族や従業員の人数に合わせた量を
- バランスの取れた食材を
- 日常に溶け込むローリングストックで
いざという時に慌てないよう、今日から少しずつ準備を始めましょう。
「食べながら備える」ことが、最強の防災対策です。