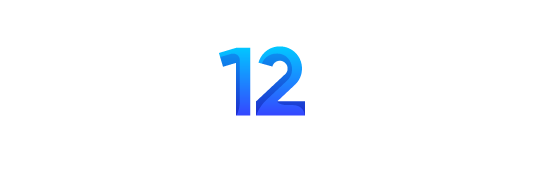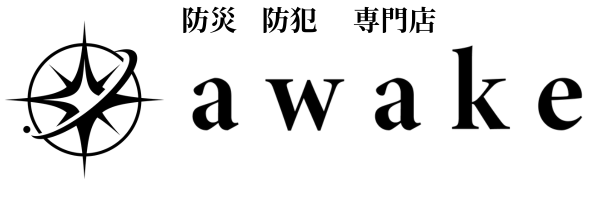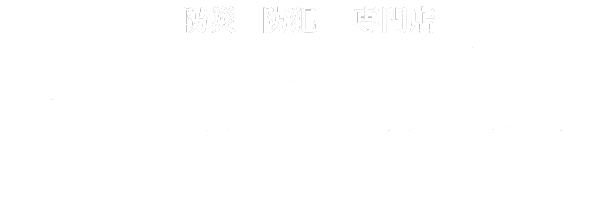毎年9月1日は「防災の日」。この日は、地震や台風、豪雨などの自然災害に対する備えを見直すきっかけとして制定されています。災害はいつ発生するかわからず、日頃からの準備が命や生活を守ります。
この記事では、防災の日に行うべき家庭・オフィスの備え、必要な防災グッズの紹介、点検・保存方法まで、具体例を交えて詳しく解説します。初心者でも今日から実践できる内容です。
もくじ
防災の日とは?制定の背景と意義

制定の背景
防災の日は、1923年の関東大震災の発生日である9月1日に由来しています。この日をきっかけに、国民一人ひとりが災害に対する意識を高め、防災準備の重要性を再認識する日として制定されました。台風や豪雨が多い時期でもあるため、災害への備えを見直すのに最適です。
防災の日の意義
- 自宅やオフィスの防災グッズを確認する
- 家族・社員との避難経路や連絡方法を再確認する
- 地域の防災訓練やイベントに参加し、災害時の対応力を高める
防災の日は「備えを習慣化する」ためのきっかけとして、非常に重要です。
防災の日に家庭で行う準備・点検チェックリスト
防災グッズの確認
- 非常食や保存水の賞味期限チェック
- ライトや懐中電灯の動作確認
- 救急セットの中身を確認し、不足しているものを補充
家族での確認事項
- 避難場所や避難経路を再確認
- 家族間で安否確認の方法を話し合う
- 高齢者やペットの避難方法も計画
家庭内安全チェック
- 家具の転倒防止対策(地震対策)
- ガスや電気の緊急遮断の確認
- 雨漏りや水害に備えた排水口の確認
防災の日に法人・オフィスで行う準備

社員向けチェックリスト
- 緊急連絡網や安否確認手段の見直し
- 避難経路・避難誘導の確認
- 社員向け備蓄品(非常食・水・簡易毛布)の点検
防災訓練の実施
- 年1回の防災訓練を防災の日に実施すると参加率が高まる
- 消火器の使い方、避難誘導、応急処置の方法を確認
BCP(事業継続計画)の見直し
- 災害発生時の事業継続手順の確認
- 重要データや書類のバックアップ状況を確認
- 非常時に必要な物資のリストを最新化
防災グッズの選び方と家庭向けおすすめアイテム
選び方のポイント
- 家族構成や住環境に合ったアイテムを選ぶ
- 賞味期限や耐久性をチェック
- 緊急時に使いやすいか確認
家庭向けおすすめアイテム
- 非常食・保存水:アルファ米、缶詰、保存水は1人1日3Lが目安
- ライト・バッテリー:LEDライト、手回しラジオ、モバイルバッテリー
- 衛生・救急用品:携帯トイレ、ウェットティッシュ、救急セット
- 防寒・雨具:ブランケット、防寒着、レインコート
- コミュニケーション・情報確保:ホイッスル、携帯ラジオ、スマホの予備バッテリー
法人・オフィス向け防災グッズと導入ポイント
備蓄品
- 社員数に応じた非常食・水・簡易毛布の用意
- 防災バッグの人数分セットやオフィス用備蓄BOX
避難・安全対策グッズ
- 非常灯、誘導ライト、消火器、簡易担架
- 重要書類・PCデータ保護用の防水ケース
導入のポイント
- 定期的な訓練と点検を実施
- 災害発生時の役割分担や避難計画を明確にする
防災訓練や防災イベントの活用方法
- 地域の防災訓練に参加して、避難経路や防災用品の使い方を学ぶ
- 学校や自治体が実施するワークショップで体験型訓練
- 防災の日をきっかけに家庭・オフィスで簡易訓練を行う
防災の日に知っておきたい防災情報・ニュース
- 気象庁や自治体の災害情報サイトを確認
- 過去の災害データをもとに、自宅やオフィスのリスクを把握
- 災害時に役立つアプリやSNS通知サービスを活用
まとめ:防災の日をきっかけに、日常の備えを習慣化
防災の日は、災害に備えるための最適なタイミングです。家庭でもオフィスでも、必要な防災グッズの準備、避難経路の確認、訓練の実施を行いましょう。
今日からできる3つのステップ:
- 家族・社員の必要アイテムをリスト化する
- バッグや保管場所を決めてセットアップする
- 定期的に点検・入れ替えを行い、非常時に使える状態を維持する
防災の日をきっかけに、日常的な備えを習慣化することで、災害発生時に安心して行動できる力が身につきます。